子どもの選択肢を広げ、自身で選び取る環境を
隅田川自治β ダイヤローグ④
会田 大也(山口情報芸術センター[YCAM]アーティスティック・ディレクター)
臼井 隆志(アートエデュケーター)
コロナ禍は、あらゆる世代に影響を与えています。とりわけ、日々の学びや成長を育む子ども達への影響は小さくありません。こうした時代のなか、アートが地域の子ども達に対して可能性の選択肢を広げることができる存在になれるのか。山口情報芸術センター[YCAM]アーティスティック・ディレクターの会田大也さんと、アートエデュケーターの臼井隆志さんとともに、子ども達の未来を生み出す文化・芸術のあり方についてお話をうかがいました。

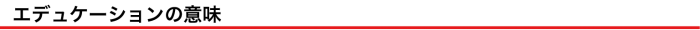
—— 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。お二人とも、アートとエデュケーションに携わる活動をされています。特に、子ども達と接する機会の多いお二人に、子どもとアートの関係性についてお話をお聞きできればと思います。
会田大也さん(以後、会田):よろしくお願いいたします。自己紹介では、ミュージアム・エデュケーターという肩書きを名乗っています。エデュケーションの語源は人々の心の中に存在する潜在能力を 「引き出す」という意味を持つわけですが、アート作品が傍らにあるミュージアムという現場で、教育的なプログラムを設計するのが私の仕事です。学校教育と区別するために、ミュージアム・エデュケーターという名称を用いています。
臼井隆志さん(以後、臼井):私は、アートエデュケーターという肩書きを名乗っています。会田さんとの違いは、普段、アートの文脈がないところでアートエデュケーションを起こすためにどうするかを考えながら活動してきました。
会田さんとは大手百貨店の新規事業で、子ども対象のワークショップなどの企画運営でご一緒した経験もあります。その事業は、子連れで百貨店に来ることで大人も子どもも安心して滞在でき、ビジネスへとつなげていくような位置づけで、色々な可能性や課題を感じる現場でもありました。特に、企業におけるアートを媒介とした事業の難しさを経験しました。こうした経験から、単純なファシリテーションだけでなく、根本的な企業の組織開発のアプローチを行いながら、組織の人材育成や組織間のコミュニケーションを円滑にするための仕事にも携わっています。
—— 会田さんは、YCAMでは行政との橋渡しなど中間的なポジションとしての難しさもあるように感じます。
会田:普段の仕事では、企業や行政、国などから支援をいただき活動しています。「成果」という意味も、お客さんが作品を楽しんで面白かった、何万人という来場者が来たというような今すぐに測定できるタイプの評価指標と、この場所に出会ったことで人生が変わった人が何人も出てくる30年後50年後といった長期的視点の評価指標とが異なることからも分かるように、どのタイムスケールの成果なのかを常に意識しながら仕事をしています。そうしたゴール設定を色んな関係者と議論しながら、公共性の高い文化投資のあり方について検討しています。いま目の前にある来場者数を増やすための手段と、将来の都市像を育むための手段は、大いに異なる場合があります。そうした話をすり合わせていく仕事は個人的には面白く感じますし、同時にやりがいも感じています。
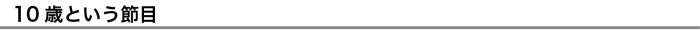
—— トッピングイーストでは、『隅田川怒涛』で子ども達と「ほくさい音楽博」を実施しました。普段触れる機会の少ない義太夫やガムラン、スティールパンといった合奏形式の音楽を、練習を重ねて発表演奏を行うプログラムです。長く続けている活動でもある中で、様々な課題にも直面してきました。お二人が子ども達とアートに関わるなかで感じる課題はありますか。
臼井:会田さんが所属しているYCAMでは、10歳以上は大人と一緒のワークショップやコンテンツに参加してもらう、という考えで運用されていると聞き、とても共感していて、いつも参考にさせてもらっています。
アートと子どもという観点で見たときに、一般的に使われる「子ども向け」という言葉の意味が、時に「子供だまし」なものに感じられて、子ども本人もそれが幼稚なものだと敏感に感じ取ることがあります。一方、子どもだけに向けられていない、大人にも届けようとしている作品を見ると、大人も子どもも一緒に感動するんです。
誰しもが、幼少期にものすごく変なものと出会ってしまった衝撃や夢中になったことはあるはずです。自分が企画を考える時も「子ども向け」とは言わず、「子どももできる」「子どもと一緒につくる」といった表現やコンテンツのつくりかたを意識しています。
YCAMが10歳を一つの節目としているのも、子ども側の、ある種の子ども扱いされることへの抵抗を感じ取っているからこそ、子ども扱いしてるわけじゃないという姿勢を示しているんだと感じます。
会田:子ども向けのコンテンツの中には、子どものことをよく観察せずにつくったものも少なくありません。それはいわば、大人の中にある子どものイメージを押しつけてつくっているようなもので、それは子どもの心には響きません。一方、よくできた動物ドキュメンタリー番組などは、特段子ども向けにはつくられていないけれども、自然の素晴らしさや生命の営みを丁寧に編集し、核心的な自然の摂理を伝えようと構成されていて、見る側の世代を超えて伝わってくるものがあるし、大人も子どももそれに引き込まれてしまう。私としては、大人か子どもかで分けるのではなく、本質的な面白さとはなにかを追究すれば、世代を超えて伝わるはずだと信じているところがあります。
子どもを対象としたものの場合、親がやらせているパターンもありますよね。親が子どもを支配しすぎて、それに慣れすぎたせいで、常に親の顔色ばかりうかがう子どももいたりします。そうではなくて、何歳であっても自立した個人として扱われる環境の中で育てたほうが良いと思います。私はこれが楽しい、と本人が心から思えるかどうか。一方的に音楽やアートを無理矢理やらせて、文化が大事です、と言うのは暴力的なことです。
もちろん、10歳までにいろんな経験やチャンスを広げるのは良いと思います。けれども、10歳を過ぎたくらいで、なんとなく自分がこれをやりたい、やりたくない、という気持ちが芽生えてくるような気がします。


写真:「コロガル公園」。会田大也さんの所属するYCAMで制作された公園型展示 撮影:丸尾隆一(YCAM)
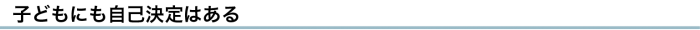
臼井:子どもにも自己決定はあります。どんなに小さくても、何かを選ぶという行為は始まっていて、親が選択肢を用意して選ぶのではなく、色んな選択肢を自ら見いだして、自らの意志で自由に選択してほしいですね。一方、子ども達の間ではゲームがますます流行してて、さまざまな影響を与えています。
会田:ゲームに関しては、中毒にさせるメカニズムが働いていて、自分が選択しているように感じていても、そうした人間の心理を突いて利用時間を増やすための設計がなされているんだよ、と説明してもよいと思います。それを踏まえた上で、それを選択するかどうかはまた別の話ですが、そうした背後のメカニズムの話はする必要があると思っています。
臼井:選んでいるのか、選ばされているのか。選ばされているという状況にどう抵抗していくのか、抵抗を当事者はできるのか。
会田:選ばされているのは、果たして選択なのか、という問題がありますよね。他にも、不用意に大人が選択肢を狭めてしまうこともやりがちです。例えば近代以降に限っても、大人が若者に対して気軽に言ってしまう一言「音楽では食っていけないよ」という言葉でどれだけ音楽を辞めてしまった人がいたことか。日本ではプロを目指す圧力も強すぎるかも知れません。もっと音楽を「楽しむ」側面を応援できると良いんですけどね。
臼井:もう一つ、ロールモデル不在の問題もあると思います。一般的に、イベントはステージと客席で分かれているけれども、ワークショップではアーティストと一緒になって、アーティストの横顔や背中を見ながらその人の音楽に対する向き合い方を感じ取ることができます。ステージに憧れるのとは違う形で、地域の子ども達にとってのロールモデルにアーティストがなっていってほしいですよね。そうした選択肢やロールモデルが増えていくことから、地域を豊かにしていく気がします。
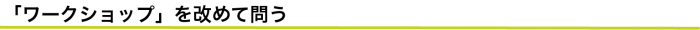
—— お二人が取り組んでいる「ワークショップ」という言葉の意味について、改めてお聞きしたいです。お二人は、ワークショップというものをどのように捉えていますか。
会田:ここ5年くらい考えているのは、価値軸の創出ということです。例えば学校の勉強の場合、縦軸に深い理解をすること、横軸に時間的に効率的に解くことというX軸Y軸の見方があって、X軸とY軸の合計値が高いことが試験では求められます。しかし、学校に行く目的はその二つだけでしょうか。例えば、Z軸に友達と会って楽しい、給食が食べられるから嬉しい、といった違う観点を置くこともできます。そのZ軸方向になにを置けばいいのか。そうした「新しい価値軸」を考えてもいい空間をつくるのがワークショップだと感じています。
よく、ワークショップ後にファシリテーターが「参加者ではなく自分自身が学びになった」と言う人がいます。それはつまり、計画した時には想定していなかった価値観がそこで生まれ、そのZ軸のインパクトが大きかったということです。一般的な学習とワークショップとの違いは、このZ軸をつくり出すことが奨励されているかどうかだと考えています。
臼井:ワークショップを表現する際、小さな意味と大きな意味があると思います。小さな意味は、教育や創作をプログラム化することで、インプットの情報を自分なりに使いこなして創作することを許容し、何かをつくり出すことの自信を高めるものです。ただ、何でも良いよ、自由につくっていいよ、という方法はワークショップとは違う気がします。ある制約や自分が知らなかったやり方を試してみて、それがファシリテーターも予想しなかったものが生まれてくる時もあります。知識を効率的に伝達するのではなく、ある種のエラーやバグが起こることを想定したプログラムのデザインがワークショップだと考えています。
大きな意味は、空間的に広がっていくものです。音楽家とのワークショップのような、音楽の道具や楽器に触れることで、音楽家やその音楽が培ってきた歴史に触れることができます。そして、触れながら自分もその歴史の一端で遊んでみることができる。そんな空間的な広がりもワークショップは持てる気がします。そうした観点で見ると、地域全体を一つのワークショップとして見立てることができるかもしれません。
会田:地域に開かれていて、そこで振る舞われている行動すべてが一つのワークショップとして設計されているみたいなことはありえますね。
臼井:そうですね。時間と空間をどうデザインするか、がワークショップと言える気がします。


写真:臼井氏の活動の様子 (上)コネリングスタディAokid公演+ワークショップ「地球自由〜!」 撮影:加藤和也、(下)コネリングスタディ「チェルフィッチュと一緒に半透明になってみよう」

会田:経験のデザイン、という表現を何度か使ったことがあります。ワークショップと一言で言うけれども、その人が感じる経験をどうデザインするか、という観点で捉え直すことで見えてくるものが沢山ありそうです。
臼井:哲学者の東浩紀さんが、デリダを引用して「誤配」という考え方をおっしゃっています。この「誤配」をどう設計するかは、アートエデュケーションにおいて重要だと思っています。
例えば美術館はアートに関心のある人がアートを目的に来ていて、そうした場所における振る舞い方が認められています。一方、そうではない場所でアートと言ってもなかなか人は集まりません。アートを目的としていないからこそ、何か違った目的でそこを訪れたはずなのに、そこでうっかりアートと出会ってしまう、これこそ「誤配」をデザインする面白いポイントです。地域に根差した場所、例えば子ども食堂やフードパントリー、縁日など、人が集まりやすい場所で誤配をつくっていくことが大切なのかな、と。
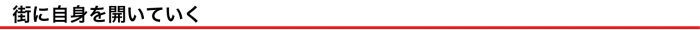
—— エデュケーションをお仕事にされているお二人ですが、ご自身のお子さんとの関わり方、近所や地域の子ども達、普段周りにいる子ども達との関わりで大事にしていることはありますか。
会田:自分の子どもには、特別なことはあまりしていないですね。けれど、理想的には自分のモノサシをつくれるような人になって欲しいと思っています。他人のモノサシで自分の価値を測らない、みたいな。そのためには、私自身が自分のモノサシで、楽しく生きている背中を見せるしかないですよね。
あともう一つ、仕事とは違う顔で地域と繋がるボランティアを大切にしています。今度、PTAの会長をやるんですよ。子どもの親として、仕事でのプロフェッショナルとは別になにか貢献できることをしたいな、と。仕事以外で付き合う人を増やし、何かしら自分が地域に貢献できることを頑張ると、結局それが良い形で仕事にも反映するはずです
臼井:仕事をしている自分以外のアイデンティティを、地域で持つことは大事ですよね。近所のおばあちゃんと会って話したり子どもを遊んでもらったりすることが、一種のケア的な要素をはらんでいるな、と感じることがあります。そうした事象に自分が置かれていることを大切にしたいです。今、自宅の庭を子ども達が遊べる場にしようと計画中なんです。自分の子どもだけでなく、近所の子ども達にも開いていけたら良いな、と思っています。
会田:以前、自宅を住み開き的なことをしていました。今も、自宅にアーティストが居候していて、家族とは違った人が入り込んでくる面白さがあります。そうした取り組みを家族も楽しんでいる様子です。
実は、「週末里親」という取り組みもやっています。お正月や夏休みのような長期休みの時だけ、数日間、里親として子ども達を受け入れるというものです。社会貢献というよりも、子ども達が個人的なつながりや絆をつくることが、預かっている子どもだけでなく自分の子にも良い影響があると思っています。里親の取り組みそのものも、山口ではまだまだ少ないのが現状です。そうした現実を知り、実際に体験してみることで分かることは大いにあります。そこから、自分が経験したことを誰かに勧めることができたらと思っています。
臼井:血縁よりも類縁という話を聞きます。類縁関係をつくることも、一つのシェアにもなりえますね。

—— 子ども達は、コロナ禍の影響を大いに受けています。そのなかで、私たちのようなアートNPOに何ができるのか、「ほくさい音楽博」を通じて改めて問われているような気がしました。
会田:「ほくさい音楽博」のように、本番があることで集中力だったりさまざまな経験のジャンプとなったりするようなものがあることは大切です。本番があってはじめて日常の練習にも意味がでてきます。かつては、地域のお祭りは一つの本番でした。まちづくりにおいて、何を本番と設計するかですね。
臼井:音というメディアの特性も特徴的かもしれません。音楽は、どこかから聞こえてくるもの、街中に漏れ聞こえることによって生まれるものがあるはずです。街という舞台で何ができるか。今は、コロナ禍で接触を楽しめない雰囲気がありますが、音であれば、聞こえてくる音にも楽しみを見いだしうる可能性があります。それは、キュレーションされたものとは違う、誤配を生み出すものでもあるはずです。音楽が地域にもたらす可能性をもっと追求していってもらいたいですね。
取材:清宮陵一、小出有華(NPO法人トッピングイースト)、編集:江口晋太朗(TOKYObeta.Ltd)
カバー写真:「ほくさい音楽博」で共演した人間国宝・竹本駒之助さんと子どもたち ©︎山本マオ
——————————————————————————————————————————————-
会田 大也
1976年生まれ。ミュージアム・エデュケーター。東京造形大学、IAMAS(情報科学芸術大学院大学)卒業。2003〜2014年山口情報芸術センター[YCAM]エデュケーター。2014〜2019年東京大学大学院GCL特任助教。2019年あいちトリエンナーレキュレーター(ラーニング)、2020年〜現在YCAMアーティスティックディレクター。国際芸術祭あいちキュレーター(ラーニング)。主な担当事業「コロガル公園」。
臼井 隆志
アートエデュケーター/ファシリテーター
企業を中心に、福祉施設や美術館、劇場など多様な場で、0歳から大人までのアートエデュケーションを専門とする。著書『意外と知らない赤ちゃんのきもち』(スマート新書)。


