即興音楽の参加性と自治の関係、そして、音楽産業の再構築
隅田川自治β ダイヤローグ⑧
細田 成嗣(ライター・音楽批評家)
若林 恵(黒鳥社 コンテンツディレクター)
コロナ禍の開催となった『隅田川怒涛』では、密を避け、また、同じ空間に観客のいない状況下でのパフォーマンスの可能性を探りました。そこでは人間の持つ即興性が大いに引き出される新たな音楽表現の可能性を垣間見ることができました。黒鳥社 コンテンツディレクターの若林恵さんと、ライター・音楽批評の細田成嗣さんとともに、音楽が持つ価値の再考から始まり、表現と自治の関係性について議論しました。

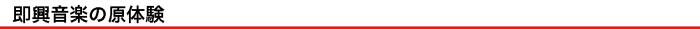
—— 今回、『隅田川怒涛』は新型コロナの影響で延期になったり、実施直前でオンラインへ移行するなど、様々な対応に追われた開催となりました。春会期のプログラムで、いとうせいこうさんら”言葉チーム”と和田永ら”家電音楽チーム”とのコラボレーションは、事前打ち合わせがあまりできずほぼぶっつけ本番だったのですが、そのパフォーマンスに人間の即興性と集中力が存分に発揮されて、とんでもない跳躍を生み出しました。その経験から、人間の即興性から地域自治を見渡すことができないものかとお二人をお招きしました。
—— まず、細田さんは即興音楽シーンで活躍されている方々とのイベントを定期的に開催されています。即興音楽に関心を持ったきっかけはなんでしょうか?
細田成嗣(以下、細田):いわゆるジャンルとしてのフリーインプロビゼーションに関心を持つようになったきっかけとしては、大友良英さんの音楽やテキストと出会ったことが一つの大きな入り口としてありました。実は10代の頃にギターをかじっていて、ふと「既成概念に囚われないギタリストはいないだろうか」と思いリサーチしたところ、大友さんに行き当たったんです。広い意味での即興音楽ということであれば、それ以前から、例えばロック・ミュージシャンがライブで楽曲を変形してしまうことに面白さを感じてもいましたが、大友さんの活動を介して、デレク・ベイリーをはじめとした即興演奏家の存在を知り、フリーインプロビゼーションの歴史を知ることになった。そして90年代後半から2000年代にかけてフリーインプロビゼーションの系譜の新しいシーンが東京にあったことも知りました。けれども、ちょうど自分が興味を持ち始めた2000年代後半頃には、そうしたシーンはもはや過去のもので、フリーインプロビゼーションなるジャンル自体が袋小路に陥っているというような言説ばかり目にする状況でした。しかし実際に現場に足を運んでみると面白いことが行われている。しかもフリーインプロビゼーションの系譜をさらに先へと推し進めているところもある。でも誰もそのことを語ろうとしません。だったら自分でそうしたシーンを紹介していくしかない、と思って執筆活動やイベント企画に取り組むようになりました。
若林恵(以下、若林):私の原体験はアート・リンゼイですね。クラブ・クワトロでアンビシャス・ラバーズが出てきて感動しましたし、フレッド・フリスもよく聴いていました。90年のアルバム「STEP ACROSS THE BORDER」に先立って上映されたフレッド・フリスのドキュメンタリー映画も良かったです。当時はソ連との冷戦構造が壊れ、80年代に始まった新自由主義が拡張していった流れのなかで、政治で分断されてた世界が一体化するイメージをみんなポジティブに思っていた時代でした。プレ・インターネット時代におけるアンダーグラウンドネットワークを渡り歩くモデルとして、フレッド・フリスの映画があったんです。ワールドミュージックが流行り、アート・リンゼイはポストロック的なアンダーグラウンドシーンと関わり合ったりしていました。新しい個人が世界を渡り歩き、その場その場でともに作り上げていく世界がそこにはありました。
—— 音楽が、音楽以上にそういう世界をまとっていた時代でした。
若林:そういうイメージを強く持っていましたが、坂本龍一さんが「ビューティ」の制作でアメリカを訪れたら全然そんな世界はなく、幻滅したとおっしゃっていました。新しいグローバルビレッジを引っ張るコスモポリタンのイメージが、90年代に次第に崩壊していくわけです。以前、細野晴臣さんにインタビューした時も、インターネットが出てきて個人が世界とつながっていくことへの期待感が次第に薄らいでいったという話をしていました。
90年代は不思議な時代で、J-POPという概念もその頃出てきました。閉じたローカルではなく、世界の中で日本をもう一度提示し直すという意味としての“J”でした。けれども、結局はドメスティック化していきます。当時は、55年体制からの大規模な政治改革が起き、民意をダイナミックに反映させていく政治主導体制がつくられていた時代でした。そういう時代のなかで、自分の中ではフレッド・フリスやアート・リンゼイはこれからの人間の生きていくモデルだったと本当に思っていました。
—— 2011年の東日本大震災の3ヶ月後、まだ震災直後で不安定ななか、アート・リンゼイさんが来日し渋谷 duoで大友さんとのセッションイベントがありました。その際にアートさんと色んな話をする機会があって、アートさんも大友さんもたくさんの人が関わるプロジェクトを試行していて、音楽が街中に出て行くあり方が多様な形で実践されているんだなと感じました。
若林:アート・リンゼイがイメージしているのは、ブラジルのカンドンブレやバイーア州でやってるようなものに近いのではないでしょうか。
—— 黒人が集まってカンドンブレを始めた場所がバイーア州で、そこから発展して地域性の高いパレードチームが生まれたりして、ギャングになった子ども達を音楽でどう更生させるか、みたいなことも起きています。そのお金を出し合うのは地域の大人達で、そこにある種の自治が生まれていて、音楽によって社会課題を解決するローカルな手法が注目されはじめた時期でもありました。
若林:政治改革では地方分権は重要なモチーフで、それこそ80年代から今でもずっと続いています。しかし、その方法が国から地方にお金をばらまくだけで、逆に集権化が高まり国に依存する体質になってしまい、自治につながっていないのが現状です。
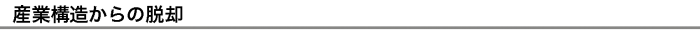
若林:即興の話に戻すと、著作権の問題は大きいと思っています。配信をやり始めて分かったのは、配信だと曲が流せず、即興なら良いという話は結構重要な論点な気がします。つまり、音楽産業における著作権を中心としたマネタイズモデルの限界がそこにはあります。もはや、ライブはただの興行で、著作権者が音源をマネタイズする一つのプロモーションのツールになってて、業界もそういう風に認識しています。ライブ体験はどれも似たようなものばかりで、コンテンツは変わってるのに体験としては何も変わっていません。基本的にライブハウスは、再現性を前提に空間も含めてクオリティを均一化させてるからそうなってしまっているのでしょう。
細田:一方、2000年代頃からフェスが主流になってきて、音源よりツアーやライブが中心になってきています。
若林:デジタル化の流れが起き、音源そのものが商品にならなくなったからライブにシフトしているだけだと思います。結局、同じようなフェスが世界中にできて、みんなぐるぐる回ってるだけのように感じます。
細田:同時に、音楽の楽しみ方自体が変化したとも言えそうです。2010年代初頭に文芸・音楽評論家の円堂都司昭さんが『ソーシャル化する音楽 「聴取」から「遊び」へ』という本を出版されていましたが、フェスへのシフトと並行して、音楽が聴取や鑑賞の対象となるものから、誰かとコミュニケーションをするきっかけになるものへと変化していった、あるいは後者の役割が比重を増していった。聴取や鑑賞という点では変わりばえのしないライブが再現されていたとしても、コミュニケーションや遊びとして捉えるなら毎回価値ある体験になる、そういった音楽の楽しみ方の変化も起きてると思います。
若林:それはあると思います。音楽それ自体より、人が集まって、そこから何か出てくることの価値にシフトしてきています。もう一つフェスの話をすると、ROCK IN JAPAN FESTIVAL がひたちなか市から千葉市に移って話題になっていますが、当事者でもある自治体側は、動員でしかフェスの価値を評価していません。つまり、経済効果をKPIとする産業構造のあり方しか見ていないのです。体験にシフトしていると言われているけれども、実際に何の価値になっているのか、改めて考え直さないと、これまでの産業構造にひたすら回収されてしまうだけです。
—— 「隅田川怒涛」も、オンライン化によって当初予定していたリアルイベントの来場者数などの数字的なものをそれほど強くは問われなくなりました。けれども、新たな評価軸をこれから考えていかないと、いつまで経っても来場者や閲覧数のような定量的なものでしか測れません。そうではなく、人の関係性がどう構築されたかを見える化できる仕組みのような、次なる評価のあり方を模索したいと考えています。

写真:「隅田川怒涛」春会期には足立区にあるスケートボードパーク場からオンラインライブ配信を行った。©︎山本マオ
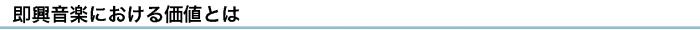
若林:色んなフェスやイベントをやる時に大事なのは、ステークホルダーが誰かということ。その時、一番重要なのはやっぱりミュージシャンのはずです。ミュージシャンにどのような価値を与えているのかを説明できないまま、フォロワーが増えるとかアルバムが売れると言われても意味はありません。例えば、即興ミュージシャンのライブにおけるKPIは何になるのでしょうか。即興ミュージシャンのライブは数百人規模と思われ、KPIは集客数ではないはずです。即興ライブでどんな価値があると満足度が高いのか。その価値が、お客さんの満足度と連動する可能性はあります。
細田:インタビューや立ち話で自分が聞いた限りでは、もちろん理由は人それぞれですが、基本的には動員を第一の目標に掲げている即興ミュージシャンはいないですね。どちらかというと質の方が大きくて、演奏で発見があったり聞いたことがない音を見つけたり、はじめての人と一緒に演奏したことで生まれる交流やそこからコラボレーションに発展する楽しさを理由に演奏している人が多いです。
若林:去年、ドラマーの石若駿さんと話した時も同じようなことを語っていました。つまり、自分が知らない何かを自己発見するプロセス、一種の成長のプロセスがミュージシャンに作用してるんだと思います。

写真:「隅田川怒涛」夏会期には、東京スカイツリー®︎の天望デッキからラップとドラムの即興パフォーマンスを披露。ラッパーとNIPPSさんとドラマーの石若駿さん ©︎三田村亮

細田:一般的なポップスやロックのライブだと、ミュージシャンがメッセージを伝えたり観客同士を団結させたり、つまり外に対しての発信が大部分を占めると思います。けれども即興音楽などある種実験的な音楽の場合は、演奏家が自分の内面と向き合ったり、仮に外に向いたとしても出した音が空間でどう響いているのか観察したりするものだったりします。
そのうえで即興音楽における観客のあり方を考えてみると、一方ではミュージシャンのシリアスな演奏にじっくり耳を傾けて聴くという態度がありますが、他方ではアート・リンゼイのパレードや大友さんが行っている指揮を交えた演奏、ポーツマス・シンフォニアの流れを汲んだ市民参加型オーケストラのような、観客がただ聴くだけではなく実際に参加者になることもあります。これもある意味で即興音楽の一つの大きな特徴で、自己研鑽的でシリアスに音楽を突き詰めていく方向の裏には、普段音楽をやらない素人でも参加できてしまう側面があります。ポップスのライブでいきなりマイクを渡されても曲を知らなければ歌えないですし、ロックやジャズのジャムセッションも急に「楽器を弾いてください」って言われても素人には難しい。しかし、「手を叩いてください」って言われて叩くだけなら参加できる。即興音楽には、そうした能力や経験を問わず参加できる開かれたあり方があります。
—— 大友さんをはじめとした参加型の音楽表現活動が、もっと社会に広まったら良いなと思います。一方で、果たしてどこまで開かれているのか、受け取ってもらえてているのか、という思いもあります。
若林:政治文脈で言うと、市民参画だけど来る人はみんなプロ市民、みたいなものが即興の世界にもある気がします。
細田:たしかにそうですね。参加者がファンや近しい人たちだけになってしまうと、結局はもともとその手の音楽が好きなインナーサークルで盛り上がっているだけになってしまいます。原理的には開かれた形ではあるので、即興クラスタの集まりにしない方法にする必要がありますね。

若林:60年代からのイギリスの即興音楽における参加型といえば、ブライアン・イーノがコーネリアス・カーデューがやっていた実験アンサンブル「スクラッチ・オーケストラ」に衝撃を受けた話をよくします。素人が演奏するけどそこにはいくつかのルールがあって、それに則った上でみんなが好き勝手やると音楽になるという話です。それはまさに自治で、最低限の制限や規制のもとにみんなが自由にやれて、かつそこに秩序が発生することがどうしたら可能なのかという命題につながります。
以前、フランスの現代音楽のオーケストラ指揮者の方と対談する企画があった時、オーケストラは軍隊がモデルだから嫌いだという話をしたんです。そうしたら、ものすごく怒られまして……。というのも、かつては軍隊がモデルの官僚組織だったオーケストラも、今は市民社会の一つのモデルを実現することを重視している、とおっしゃっていました。それはダイバーシティともつながってて、誰を楽団員として採用するかにも関わってきます。かつての指揮者は統率する将軍のイメージで、楽団員は手兵と呼ばれていた時代もありました。しかし今は、どんな演目をやるのかを民主的に合意形成しています。社会のモデルの反映のもとに進化しているという話を聞いて、いたく感動しました。
イーノの話に戻ると、最低限の規制で最大限の自由を発揮させ、かつカオスにならないことを可能にする話は、まさしくインターネットをどう制御するかという話と完全に連動しています。今はフェイクニュースやヘイトだらけになるなか、表現の自由も担保しなければなりません。一方で、ネット上は参加型やコラボレーションが活発で、早々に民主的な動きも生まれていて、このインターネット空間のあり方をどうするかが私たちも問われています。イーノがコーネリアス・カーデューのことをずっと言い続けていることに、とても好感が持てるんです。
細田:市民社会のあり方を疑似的にモデル化することでいうと、ジョン・ゾーンのCOBRAが民主主義的なシステムを集団即興で体現する一つの究極型として知られています。ただ、COBRAはやはりゲームとしての側面が強く、参加者が楽しむぶんにはいいですが、次へつながるものにどう落としていくかを考えると難しい。それにCOBRAに参加するためには高度な演奏技術も要求されます。なので、素人はただ鑑賞するしかありません。そうではなく例えば、参加型ワークショップやオーケストラを地域でやる際に、その地域住民とどう交流し、その地域に残るものを築けるか、ということがすごく大事な気がします。
若林:COBRAが面白かったのは、仕組みを使って好きにしていいって立て付けで、日本だと巻上公一さんが取り入れていましたね。仕組み自体が一種のコモンズのような考え方は今でも有効だと思います。
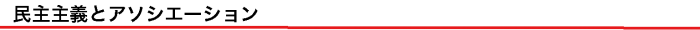
若林:民主主義について、政治学者の宇野重規さんがトクヴィルについてまとめた本を以前読んだことがあります。フランスの政治家のトクヴィルは、1831年にアメリカに渡って民主主義について考えた人です。トクヴィルは、民主主義はある種のパラドックスを抱えてると指摘しています。それは、全員が個であることが前提に立っているため、他者に依存することができず分断されていて、その結果大きなものへ依存してしまうという。コロナ禍で起きたことも同じで、本来なら困ってる人がいれば身の回りの人が助ければいいのに、自分がやりたくないから誰も助けようとしません。そのかわり、国には補助金を出せと言って、より大きいものに依存しています。そうした考えが実は矛盾してる状態だという根本的な問題は、約200年経つ今でも有効だと思います。
そこでトクヴィルは、民主主義に潜むパラドックスに対抗する一つの仕組みとして「結社」、いわゆる”Association”が、分断された個人をつなぐ紐帯だと言います。アメリカでは教会を中心とした空間やコミュニティのもとに、異質な他者と出会う機会になっています。ある価値観のもとに自由に集うことを社会の中に差し込むことで、民主主義社会がはらむ暴力性や専制政治に対する抑制や監視、抵抗の拠点になりうるものだと感じます。そうした参加のあり方は、音楽でもあり得る気がします。
—— そうしたときに、一つの結社、アソシエーションにおけるスケールアップはあまり気にしなくてもよいのでしょうか?
若林:結果として大きくなることはあっても、スケールが目的ではありません。それでいうと、BTSのコミュニティは面白いですね。ファンクラブが、ある種の規範をもとに自律的に運営されていく新しいモデルです。そのコミュニティが社会性を帯びていくと、必然的にBLMにどう向き合うかを考えたり、気候変動についてBTSも気にしてるということがきっかけでみんな勉強し始めたりします。最初から政治的な結社として成立したわけではないものの、結果として社会に対して何かしらのスタンスを取るようになっていくんです。
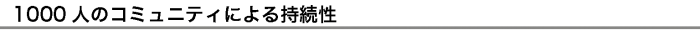
細田:先日、カンパニー社という独立系出版社で代表を務める工藤遥さんと対談させていただきました。カンパニー社はアルバート・アイラーやコレット・マニー、ハリー・スミスといった、あまり一般的ではないマイナーな対象を取り上げて本にしている出版社です。その時に工藤さんがおっしゃっていたんですが、ケヴィン・ケリーの「1,000人の忠実なファン」というテキストを引き合いに出しつつ、クリエイターだけでなく出版社もコアな読者が1000人程度いれば持続可能なはずだと。無闇矢鱈にスケールする必要はないと。そしてそのコミュニティは固定メンバーである必要はなくて、ある程度流動的であってもいいと。その話を聞いて、これはまさに即興音楽シーンの規模感と一緒だなと思ったんです。そうしたコミュニティが小規模でも持続することで、社会性と向き合うきっかけが生まれるという道筋もありそうです。
若林:コミュニティーの一員になりたいという欲求は、もはや消費ではなく主体的な参加へとシフトしています。コミュニティへの参加と関連すると、教育の機能が社会からどんどん薄くなってる気がしています。成長の機会を学校が担保できず、会社の中にそれを埋め込んで、入社して社会人としてのノウハウや社会の複雑性を学ぶように以前はなっていました。しかし、会社も余裕がなくなってきたので、スキルを持ってる人しか採用できなくなりました。若い世代は、会社の中にいると外の情報が入ってこなくて自分の成長ができず、だから外に出ていくという現象も起きています。
音楽評論家・ライターの柳樂光隆さんらと編集者やライターの勉強会「音筆の会」を開催した時、会社にいても誰も編集を教えてくれず、自分がやってる編集が本当に正しい編集なのか分からないという不安を抱えた人たちが多く集まってきました。これも一種の結社みたいな形で、教育というほどではないにせよ、自分がやってることを相対化する場があることは大事だと思います。
—— 仕事ではなく、色んな集まりがあちらこちらにあることでクリエイティビティも発揮され、そうした場が増えてくることで多様性が生まれてきそうです。
若林:日本はエスタブリッシュメントと草の根で二層化してて、中間がほぼないと思います。一方、草の根の多様性はものすごくあります。日本の市民社会の活力は50、60年代において鶴見俊輔さんがサークル研究、今の同人誌のようなものを研究していて、そうしたコミュニティは戦後から今もずっと存在し一向に廃れていません。例えば、それぞれの地域には必ず郷土史家や郷土玩具を集めた人がいて、地元郷土史の専門出版社で本を出すのが根強くあります。市民社会を考える時に、このあたりがもう少し再構築できるといいのでは、と思いますね。
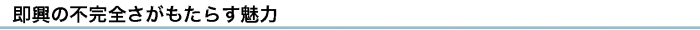
—— コロナ禍で、人が直接的に集うことが難しくなったため、オンライン配信が爆発的に増えてきました。『隅田川怒涛』も全国各地、世界中から観てもらえましたし、ミュージシャン自らが積極的にライブ配信するケースも多くなりました。
細田:以前からライブ配信そのものはありましたが、コロナ禍以降、即興音楽シーンでもリモート・コンサートに取り組むミュージシャンが相次ぎ、私もいろいろと観るようになりました。ライブ配信はフィジカルな空間を完全に代替することはできないですが、普段のライブではできないオンラインならではの試みが可能になるので、そうした表現が出てきたことは面白いと感じました。ただ、最近はライブ配信が代替し得るライブ性も丁寧に見ていく必要があると思っています。
例えば生配信であれば、パフォーマーと視聴者の間で時間が同期しています。そこには不可逆的な一回性やインタラクティビティがあります。このうち一回性に着目すると、THE FIRST TAKEのような生配信ではない一発録りの映像にライブ性を見出すことができます。生配信でも一発録りでもなくても、パブリックビューイングで視聴すれば、フィジカルな空間のライブ性を共有できます。今後はオンラインならではの試みのさらなる探求がある一方で、作品にどのようなライブ性を持たせられるのかが一つの課題になりそうな気がします。
若林:ライブ性について、DOMMUNEの宇川直宏さんが三つの現場があると言っていました。一つが配信している現場、もう一つがそれぞれが見ている現場、最後がTwitterなどのSNSや動画のチャットコメントといった外部性です。しかもそこに投げ銭ができる仕組みがあることで、よりライブ性を高める仕掛けになっています。
—— ライブコマースで稼いでいる人も増えましたね。ミュージシャンもライブ配信で相当な売上を立てる人も出てきました。
若林:ライブでは即興性がより大事になってきます。ミュージシャンがライブ配信する時に難しいのは、同じセットリストは1回しかできないということです。今までのツアーのように同じセットリストを使い回して再現性を高める効率化とは逆で、オンラインになった瞬間、場所やセットリスト、曲調を変えて今までと違うことが求められます。タイニー・デスク・コンサートやTHE FIRST TAKEみたいなものが重要なのは、音源とは違うアレンジや立て付けで新しいコンテンツづくりにチャレンジできるということに意味があるからです。
細田:再現性とは別の観点から見るなら、そもそも、演奏という行為自体が即興的に行われるものなので、ライブには常に音源とは違うある種の不完全さがあります。タイニー・デスク・コンサートやTHE FIRST TAKEも、不完全だから音源とは違うし、それを聴く楽しさ、即興的な行為ならではの魅力もあります。また、それを観てる人たちがYouTubeのチャットで会話することも、いわば即興性のある行為でもあります。カーデューが言う最小限の制約でどう自由を実現するかという話をネットに置き換えたら、動画をYouTubeで出すというある種の制約の上で、チャットで生まれる即興性みたいな自由もある気がします。

写真:「隅田川怒涛」で即興演奏をライブ配信するスタッフ ©︎鈴木竜一朗
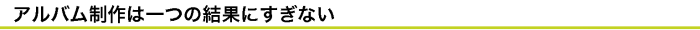
若林:そうした趨勢が、今度は音源製作にも向かっていく気がします。今までの作品はツールボックスという考えに強く縛られていて、作品はこれしかないという結論に至った上で出されるものだと思っていました。けれども、先日観たポール・マッカートニーのドキュメンタリー『マッカートニー3,2,1』では、思いついたからこれをやってみるといった即興性の高いやりとりが、レコーディングの現場で行われているんです。つまり、作品はあらゆる可能性を検討したものではなく、プロデューサーがこの人をアサインした、エンジニアは誰々、ここでレコーディングした、といった一連の結果そうなったものの産物でしかないのに、商品の立て付けはそれが隠されてしまっています。
例えば、ビッグ・シーフは一個のプロジェクトとしてアルバム制作を捉えていて、ロックダウン中の2020年夏のアメリカで、5ヶ月間アメリカ横断しながらレコーディング・セッションしたものをアルバムにして、ちょっとしたドキュメンタリー的なものになっています。もちろん、ライブをやる時はアレンジを変えて演奏します。レコード音源されたものはあくまでその時の結論であって、ライブとは全然違うものという前提に立っているんです。そうした観点に立つと、ミュージシャンはみんなBandcampやSoundCloudに日頃制作したものをばんばん上げるべきです。作品という捉え方ではなく、ミュージシャンがいかに音楽とともに生きているのかを表現できるはずです。
細田:おっしゃる通りだと思います。いわば西洋近代的な普遍性を作品に見いだすのではなく、あらゆる作品は偶然性に根ざした一種のドキュメントであると捉えると、これまでリリースされてきたさまざまなアルバムの価値も、色んな可能性のうちの一つがたまたまそうなっただけ、という新たな見方に変わってきますね。
若林:これは結構大きいと思います。産業的な枠組みでアルバムやライブが縛られてきたけれども、もっと相対化できると思います。その時に、お客さんがお金を払う意味、コンサートに期待するものを担保しつつ、何をどうずらしていくか、企画側が問われてきますね。

—— 最近では、音声主体でいつでもどこでも聴けるポッドキャストを深掘りする動きもあります。また、バイノーラルやASMRのような、自分の身体や空間に作用するものの価値も見いだされています。
若林:坂本龍一さんがおっしゃっていた話ですが、音源は基本的にVRなんです。音はバーチャルだけど人為的に空間を構成し重ね合わせるから、例えば今ここで音源を鳴らしたら一種の体験になりえます。ヘッドマウントディスプレイがなくても、VR的な世界を構築できる強さがあるんです。
細田:音がVR的であるというのは、聴覚の仕組みとも関わっていそうです。耳は進化の過程で、魚の触覚的な器官が発達して聴覚になったと言われていて、実際に鼓膜は震えてますしすごく触覚的な要素があります。音を聞くことを音に触れることだと解釈すると、空間にVR的な別の世界が物理的に構築されていると実感できる気がします。それと、音響機器と違って聴覚は基本的にスペックが変わらないので、聴取体験はあくまでも身体的なレベルでプリミティブに作用します。即興音楽の場合はそれ自体が身体的でプリミティブなものでもあり、VR的なライブ性もよりプリミティブに作用すると思います。
若林:これまであまりアンビエントは聞かなかったのですが、コロナ禍の生活でアナログを聞くようになりました。そうしたら、妙に体への作用が違うなって感じるようになりました。最初はあまりうまく説明できなかったのですが、最近思うのは、これは温泉だ、という結論にたどり着いたんです。いわば、身体にじわじわくる感じです。それに近いかもしれません。
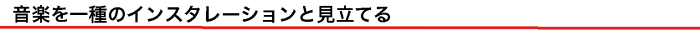
若林:音質やライブ性で言うと、フィールドレコーディングが増えていますね。録音時の一回性がそこにはあって、その面白さにミュージシャン側も気づき始めています。SpotifyやBandcampに、その辺で録っただけの音源がたくさんあって、それらがある種のセラピーのように聞こえてくる時があります。音楽がこれまでとは違った機能、それこそ生理学的な機能や、薬まではいかなくてもサプリみたいな機能が開発されている流れはある気がします。大昔で言うと、神聖ローマ帝国時代のヒルデガルト・フォン・ビンゲンのような、キリスト教におけるヒーリングや薬草、それに音楽が組み合わさって、人間の全体性を快復させていく癒やしとしての音楽や、どこかの部族の戦いの音楽のような、ある種の文化人類学的な意味も含まれているはずです。
細田:即興音楽シーンでも、最近はフィールドレコーディングを取り入れるミュージシャンが増えました。つまり環境音が含まれているので、どんな空間で音楽を聞くかが作品の体験と密接に関わってきます。リスナーの聴取環境をあらかじめ考慮しようとするミュージシャンもいて、すると単に高精細なら良いわけでもなくなります。どんなに音にこだわっても、スマホで聞かれたら意味がないですし、逆にスマホで聞かれることを前提に制作するというような。そのために適切な機材や道具を踏まえてレコーディングするという制作活動と、バイノーラルやASMRみたいなものが接続できるのかもしれません。
若林:去年、中国のエレクトロニカのアーティストがリリースしたアルバムを買った時、アルバムと一緒に変なツボをBandcampで限定個数で販売していました。それがあっという間に売り切れたのを見て、これは面白いな、と思ったんです。つまり、音楽が一種のインスタレーションとして考えられているんです。もちろん、ある意味ではマーチャンダイズの側面もあるけれども、それが作品と密接に関わった表現だからこそ、そのツボを部屋に置くことで空間性が出てきます。音源をインスタレーションと見立てるということは、そのアーティストがライブを行う際は、単純な演出ではなく空間全体の体験設計のために物を配置することでしょう。これは面白いと思います。
取材:清宮陵一、小出有華(NPO法人トッピングイースト)、編集:江口晋太朗(TOKYObeta.Ltd)
カバー写真:即興の醍醐味を魅せた和田永さんといとうせいこうさんの共演 ©︎山本マオ
——————————————————————————————————————————————
細田 成嗣
1989年生まれ。ライター/音楽批評。編著に『AA 五十年後のアルバート・アイラー』(カンパニー社、2021年)、主な論考に「即興音楽の新しい波──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」、「来たるべき「非在の音」に向けて──特殊音楽考、アジアン・ミーティング・フェスティバルでの体験から」など。国分寺M’sにて現代の即興音楽をテーマに据えたイベント・シリーズを企画/開催。
若林 恵
黒鳥社コンテンツ・ディレクター。平凡社『月刊太陽』編集部を経て2000年にフリー編集者として独立。以後、雑誌、書籍、展覧会の図録などの編集を多数手がける。音楽ジャーナリストとしても活動。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。2018年、黒鳥社設立。著書・編集担当に『さよなら未来』『次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』『GDX :行政府における理念と実践』『だえん問答 コロナの迷宮』『働くことの人類学【活字版】』など。「こんにちは未来」「blkswn jukebox」「音読ブラックスワン」などのポッドキャストの企画制作でも知られる。


