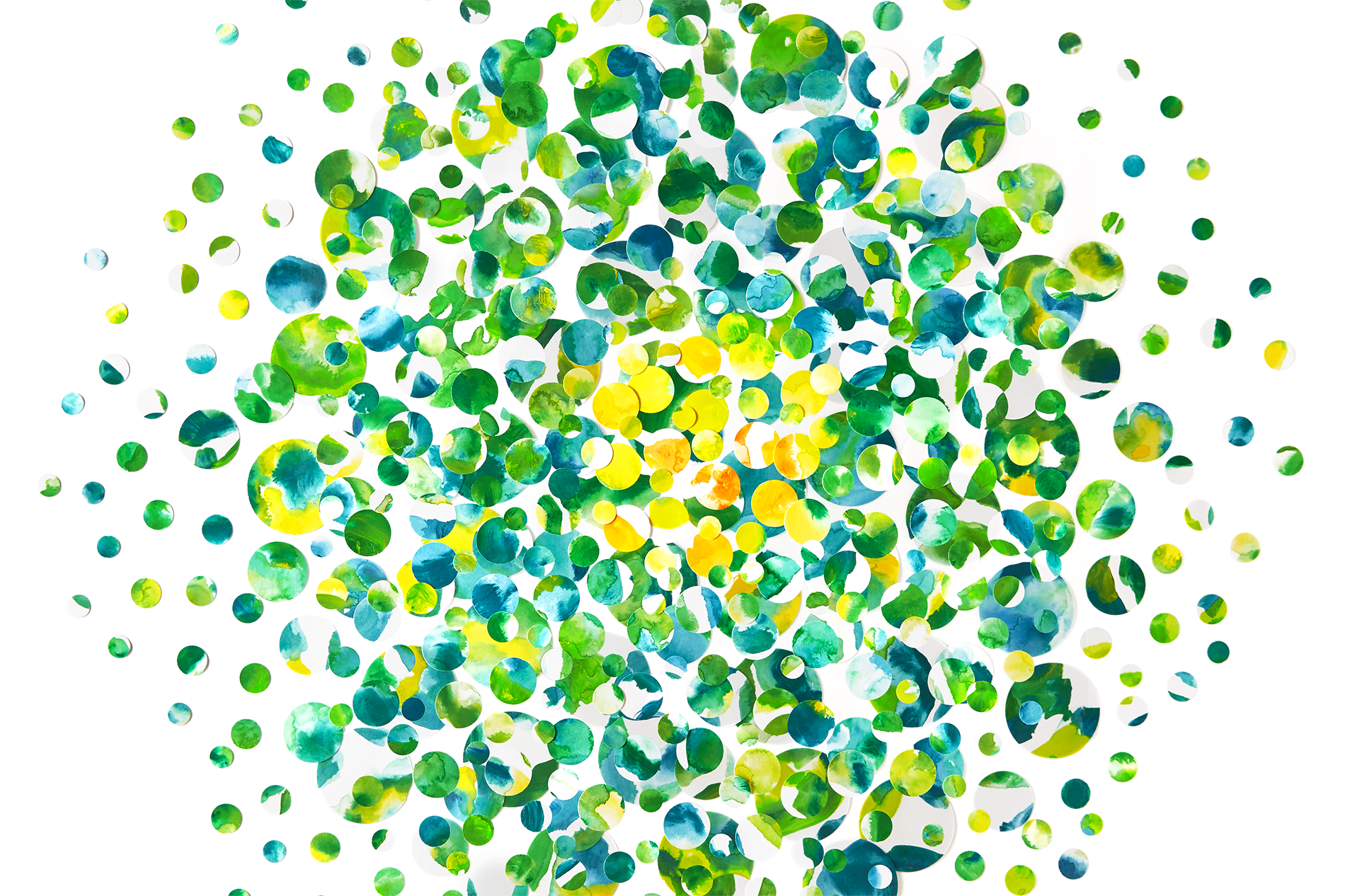2021年10月 寺尾紗穂 BLOOMING EASTリサーチレポート第2回 女工哀史とキリスト教
東東京を舞台に、アーティストが自身の興味関心をもとにさまざまな人に会い、さまざまな場所に赴き、リサーチをしていくプロジェクト「BLOOMING EAST」。
ミュージシャンで、文筆家の寺尾紗穂が、東東京の知られざる歴史や消えゆく声に耳を傾けるエッセー・シリーズです。
第1回はこちら
籠の鳥より監獄よりも
寄宿ずまいはなお辛い
工場は地獄よ主任が鬼で
廻る運転火の車
『女工哀史』は1925年改造社から出版された細井和喜蔵によるルポルタージュだ。細井自身が紡績工場に機械工として勤めていた。パートナーの高井としをも紡績女工であり、この2人の経験と見聞をもとに描かれている。1920年としをは東京モスリン(羊毛)亀戸工場に入社している。東東京はかつて今よりも水路が多く、出来上がった製品を運び出すにしても、原料を運び入れるにしても適しており、多くの工場が林立していた。
『女工哀史』の巻末には、女工たちが実際に歌っていた歌を採譜したものが、収録されている。採譜は「海ゆかば」の作曲で知られ、当時東京芸術大学で教鞭をとっていた信時潔だ。かつて、貧しい家の子供たちは他家に子守奉公に出された。守子と呼ばれる彼らは、奉公先でも冷遇されることが多く、日本には沢山の「つらい苦しい、家に帰りたい」という「守子(もりっこ)」たちが歌った守子歌が残されている。これが明治に入り、彼らが街の工場に入っていくと、女工の歌に代わっていった。『女工哀史』巻末に記録されたいくつかの歌は、あきらかに守子歌の系譜と思われるものも散見する。
皇室の仕事として、「ご養蚕」が正式に組み込まれたのは明治4年昭憲皇太后による導入に端を発する。紡績は新生日本にとって重要な殖産興業であった。多くの工場が生まれ、多くの女工が生まれた。『女工哀史』を読むと、初期の紡績工場の過酷な実態が浮かび上がってくる。1930年に23時以降の深夜労働が禁止される前は、12時間労働が当たり前であり、夜間も操業した。寄宿舎で一枚の布団を昼番と夜番の2人の女工が使ったという。
貧しい農村から出てきた少女以外は辟易するような粗末な食事と長時間労働にさらされ、肺病も蔓延した。こうした工場の現場をいち早く改革していった代表的な企業は鐘淵紡績であった。後に社長となり、「温情主義」として知られた労働者優遇の改革を展開していった武藤山治は、1894年勤めていた三井銀行から鐘紡の兵庫工場支配人に任命される。また武藤を助けて1900年から東京工場の改革に取り組んだ藤正純も、勤めていた三井銀行からの任命だった。武藤はアメリカ留学を経た開明的な人物であり、一方の藤は大分の貧農の出で、小学校も中途退学せざるを得なかったという経歴ながら、人格の高潔さで知られていたようだ。武藤が入る以前、鐘紡は「借金王、貧乏会社」と言われ、絹の質も粗悪だったという(『藤正純奉公話』)。おそらく、女工たちの待遇も『女工哀史』と似たり寄ったりであっただろう。
しかし、『女工哀史』が出た1920年代、鐘紡の工場は変化していた。1919年の鐘紡兵庫工場では、寄宿舎も美しく、新しく建築中のものもあるうえ、献立も充実して「自由供給」、つまりおかわり自由であった。女工たちはお化粧をする余裕もあり、「浅草辺に近い工場の女工」とは違う。工場の敷地内には、菓子屋や散髪屋、公園もあって一つの町のようになっていた(「鐘紡兵庫工場」『労働世界』)。武藤が兵庫工場に来てから25年がたっていた。しかし、1930年には、原哲夫『鐘紡罪悪史』という本も出ている。これには、女工が格落ち品を作ると鋼鉄のスパナで殴られたこと、格落ち品を見逃してくれるよう検査方に菓子を渡して買収していたこと、病気で休むと人事係と医師によって病気退社にされること。機械の進化に伴い、女工が半数ほどに削られ容易に解雇となること。午後4時から午前2時半の10時間半におよぶ夜勤の手当が1926年には大幅に削られたこと。このような辛い状況が記された。この本が出た年、東洋モスリンでは女性労働史に残る大規模な争議があった。世相を映してタイトルも糾弾調であるが、実際、鐘紡の内部改革にはどのような改良と、どのような限界があったのだろうか。
藤正純が東京工場に赴任した1900年、「バーン先生」と親しまれた宣教師、スーザン・バーンファインドが来日している。ここから鐘紡が女工たちの福利厚生の一環の中にキリスト教の宣教と音楽を取り入れていく歴史が始まるのだ。それは会社の本流となることはなかったが、戦後も地元の教会と女工たちの交流に讃美歌という音楽を通じてひそかに引き継がれたようにも思える。

1870年生まれのバーンファインドは、ドイツ生まれの両親を持ち、幼少時にアメリカへ移住した。大学を出たのち、彼女は婦人伝道協会に日本への伝道を申し出、1900年に派遣された。10月東洋汽船の「日本丸」に乗って30歳のバーンファインドは横浜に到着した。来日から1年後、鐘淵紡績の藤工場長の求めで、3,000人の労働者がいるという工場に出かけることになる。2,000人が向島工場の寮に住み、1,000人以上がその周辺に住んでいた。バーンファインドは、下谷教会の牧師を通じて藤を紹介される。バーンファインドの伝記には次のように書かれている。
藤サンは、クリスチャンではなかったが、バーン先生という人が居るということを聞いて、彼の工場に彼女を連れて来てくれるよう、牧師に頼んだ。彼は、従業員に彼女が話をすることを望んだのである。(中略)たいていは十代の数百人が、工場の広い食堂に集まった。全員が着席してから、藤サンは、バーン先生を紹介した。「立派な先生に起こしいただいて、うれしく思います。先生は、アメリカの宗教についてお話いただくために、お見えになりました」アメリカの文化と物質主義はキリスト教信仰と相並んでいるという時流の観念が、彼に反映していたのである。
(ローウェル・メッサーシュミット『愛の泉の百年 バーンファインド宣教師の伝記』、以下『愛の泉』)
1921年から鐘紡紡績の経営者となった武藤山治も、倉敷紡績の経営者であった大原孫三郎もキリスト教的企業経営を行った。これについては、「工場制工業」が「近代化」ないし「西欧化」を象徴したこと、工場経営者にとってはその思想的背景にあるキリスト教受容に積極的であったこと、当時の労働者の労働条件の悪さなどから正義感にあふれた経営者はキリスト教を通じて救済の根拠をもとめたことなどが指摘されている(辻井清吾「日本の近代化におけるキリスト教的経営のあり方」『日本経営倫理学会誌』)。現在の感覚からすると、企業とキリスト教の組み合わせは不思議な気がするが、「西欧化」を目指した経営者が、労働者の福利厚生などを考える際に、キリスト教的人間愛を基本の信念にしようとしたことは理解できる。こうした武藤の考えと藤の考えは共通していた。「彼(藤)にとって、キリスト教信仰は、功利主義的なものであって、それは何か労働者のためには良いことで、従って工場のためにも良いことだというほどのものであった」とバーンファインドの視点で、冷静に分析されているのが面白い(『愛の泉』)。
藤は、工場での女工たち向けの大規模な会のみならず、彼女たちをまとめる女性監督者の会、幹部の奥さんたちの会と「バーン先生」を小さな集いと次々結び付けて、指導を依頼している。彼女が、1909年に日曜学校を開く部屋が欲しいと言えば大きな部屋を用意し、教会を作りたいといえば同意し、さらに「ここで一日中働く親たちの子供のために、幼稚園もほしいと思います」と付け加えた。この幼稚園の構想が、バーン先生からではなく鐘紡工場長の側から出たことに驚きを感じるが、これには、武藤三治の息のかかった鐘紡兵庫工場工場の進歩的な福利厚生が念頭にあったと思われる。兵庫工場では1903年には無料の保育所がつくられており、1905年すでに無料の幼稚舎が設置されいた。この背景には1902年に「初紡科ニ於テ熟練工女ニ欠乏ヲ来シ」という状況が生じ、どうやら子持ち女性が他に預ける経済力がなく辞めているということが注目されたのだ(矢倉伸太郎「日清・日露戦間期における鐘紡紡績株式会社の労務管理について」『産業と経済』1995年1月)。東京本店は兵庫工場に後れを取っていた。本店の改革が遅れた背景ははっきりとは分からないが、矢倉によれば1889年の鐘紡紡績の操業開始から11年間は東京本店とそれ以外は操業規定などが全く別であり、藤が工場長となった1900年から東京本店もようやく同規定に組み込まれ、兵庫工場支配人であった武藤の傘下に入ったということが挙げられるかもしれない。ともかく、開明的な藤は積極的にバーンファインドなど教会側と協力関係を築き、福利厚生を進めようとしていた。
しかし、これもどうやら長くは続かず、藤が1921年に常務取締役となって工場長としての現場を離れたあたりから状況は停滞したようだ。『愛の泉』には「ある聖書婦人」による「一九二〇年代の記録」が引用してある。
哀れな女工たちが送った惨めな生活は、ほとんど想像を絶する。構内を歩くと、彼女たちの生活条件がいかに劣悪なものか、見て驚かされる。彼女たちは、大きな、汚い部屋をともにし、(中略)夜間にも厳しく働かなければならない。大勢の青白い顔の少女たちが、そこかしこに横たわっている。(『愛の泉』)
脱走していく女工たちも一定数いた。脱走の相談が、小さな集会の関係者に漏らされることもあり、そういう時には説得の人員が教会関係者の中から送られたという。武藤三治や藤の方針を追っていくと、女工の悲惨はごく初期のみであり、鐘紡においては順調に改革が進んだと結論付けたくもなるが、そう単純な話でもないようで、1930年に『鐘紡罪悪史』が出版されたことも、それなりに理由があるように思われる。近年、『女工哀史』によって作られた悲惨な女工イメージは、一人歩きした「実際は相応な福利厚生がなされていた」という、「社史」をもとに再検討するような報告が出てきているが、時期別の現場の声も十二分に調べられなければならないだろう。

藤が快諾したものの、教会の敷地探しは断られ続け、難航した。周辺住民にキリスト教への理解があるわけではなかったのだ。結局、工場敷地の内部に幼稚園を併設した教会が作られた。鐘紡が提供した土地は道路より5メートルほど低い場所だったので、藤が自腹で土を盛って埋め立てたという。教会は1913年7月に完成、これが向島福音教会である。後にここで保育と宣教にたずさわるゲルトルード・キュックリヒは1922年に来日、まずは小石川白山教会で日本語の勉強と宣教に取り組み、やがて向島教会に配属された。ここから藤崎五郎牧師夫妻とキュックリヒの交流が始まるが、翌年は関東大震災である。教会周辺も当然被害が大きかった。ドイツの父からの帰国を求める電報には従わず、キュックリヒは、焼け残った教会に罹災者を迎え、給食係として動き始める。バーンファインドは震災の翌年帰国することになり、鐘紡に作られていた託児所はキュックリヒが引き継ぐことになった。道具も砂場もなかった託児所を整え、鐘ヶ淵教会託児部としてスタートをきったのだ。キュックリヒは荒廃した焼野原のなか朝顔を育て始める日本人に感銘を受け、日本に根を下ろす決心をしたともいわれる。このことにちなみ、キュックリッヒが埼玉県加須に開いた戦災孤児のための施設「愛泉寮」から発展した社会福祉法人「愛の泉」では、8月には養護老人ホームで朝顔共進会という会を持つという。
1924年には罹災した教会も立て直された。当時の牧師の藤崎五郎夫妻、彼の子供たちも少しずつ生まれ、最終的には6人の子がここで育った。第1回キュックリヒの回で触れたが、五郎の孫世代にあたる藤崎悦児さんや、6女愛香さんの娘である潮田花枝さんら、キュックリヒを知る最後の世代が、「愛の泉」の運営を継いでいる。2018年の訪問時に、悦治さんや花枝さん、花枝さんの母で五郎さんの末娘である愛香さんと共に、当時92歳だった1926年生まれの五郎の長男藤崎信さんに初めてお会いし、翌年、改めてお話を伺いに行った。信さんの生まれた年に、キュックリヒは東京保育女学院(のち東洋英和に合併)を設立している。再建されたばかりの向島教会で育った信さんは、当時の向島や工場の記憶、さらには千葉の学生時代、世田谷での兵隊時代の話などを色々と聞かせてくれた。
「近くの綾瀬川は100メートルもなくてよく隅田川で泳いでたの。ボラやフナが沢山いて魚取りに。玉網ですくえたんです。家では泳いじゃいけないと言われていて、夕方一人で泳いでた。産毛に汚れがついて、昭和10年代って汚かったんだとわかる訳です。お風呂はあったけど、近くの大江戸湯には友達と行って、だれが向こうまで泳げるか、プールみたいにね。楽しみだったね」
鐘紡の工場については、信さんは思うところがあった。
「今考えてみるとね、当時女工さんが2,000人くらいいたけど、(周辺住民が)見かけないようにしてたわけ。会社が。学校に行くとき、高い塀がある。その横を通っていく。塀で何も見えない。地下道があって寮との行き来も見えないようになっていた。そのころは僕も勉強していなかったから、そういう生活がどうなのかなと」
キュックリヒさんについては、毎年彼女の誕生日に子供たちはプレゼントをもらったという。
「12月25日がキュックリヒさんの誕生日で、毎年大変なごちそうによばれてね。次の部屋にはそれぞれ名前の書いてあるプレゼントもらって、とても親しくしてもらった。水曜には私たちのところに来て一緒に生活した。だから、母が病身で愛香がキュックリヒさんに育てられたというのも、そんなにおかしいことじゃない」
キュックリヒを親代わりに育った愛香さんは、子供たちの中で最も多くの時間をキュックリヒと過ごした。
「料理も音楽も掃除も洗濯も知識もなにやっても上手だったのね。軽井沢に家(軽井沢愛泉寮)があって、職員がみんな行ったとき、全員分の料理を作って待ってた。そういうのがすごく自然にできる人なのね。料理中は心が洗われるといってぱっぱか作ってね。ピアノも歌もうまいし万能でしたね。話も上手で、みんなの心つかんで泣かせて。努力家で、朝早くから勉強して講演の準備をして。日本語も達者でした、暗記して暗記して暗記して」
信さんが後に今治教会に副牧師として赴任していたとき、キュックリヒが講演の帰りに寄ってくれたことがあった。
「ちょっとしたアナウンスで、大勢の人がそこにあつまってね。来た人に満足を与えるお話をしてね。とても有能な人でしたよ。宣教師というのは二種類あって、一つは普通の専業宣教師、もう一つは自分の賜物を活かしてやる宣教師。キュックリヒの場合は教育や保育を活かして宣教した」
バーンファインドや藤が蒔いた女工の子供たちのための幼児教育・保育の種が、キュックリヒに受け継がれ、大きく育てられたと言えるだろう。
「鐘紡は300坪を幼稚園、教会などのために無償で貸してくれたわけです。ところが戦争が始まって、教会や幼稚園をどいてください、となった。だから僕思うんだけど無償はだめ。絶対だめ。失礼しちゃうよ、工場長が安い社宅を作り、そこに押しやられた。紡績が軍事になった。野砲、薬莢工場になった」
その後、信さんは向島を離れ、キリスト教セブンスデイ系の三育学院に入学し千葉で寮生活が始まる。自然豊かなキャンパス内では、農業や芝生刈、牛の世話なども生徒が行うユニークな学校だった。あるとき、黒白のホルスタインがアメリカからやってきた。それまでは茶色の牛だったが、ホルスタインに比べると乳の量が圧倒的に少ない。茶色の牛は「朝鮮牛」と呼ばれていたことを信さんは覚えている。
「朝鮮人の生徒もいたんですよ。朝鮮牛って悪口ですよね」
牧師の子供を含む学校で、朝鮮人、ハワイからの生徒、満州から来ていた人もいた。西洋の先進的な教育方針をもち、国際色ゆたかな学校でさえそのような陰口がたたかれていたことに驚かざるを得ない。
「みんな愛国的だった。本当の愛国心があれば戦争に反対しなければならなかったが、そういう友達はいなかった。時代に流されていた。牧師を育てることが趣旨の学校でしたけどね。聖書の読み方が大事ですよ」
三育学院と聞いて思い出したのは、1932年7月から2年たらず、杉並天沼の三育女学院に留学したパラオの良家の娘マリア・ギボンのことだった。マリアは、パラオに滞在していた民俗学者・彫刻家の土方久功と知り合い、その調査に協力しながら親交を深めた女性だ。土方の家で作家の中島敦とも知り合い、中島は「マリヤン」という小説を残し、これは大学生の私が「南洋」と出会うきっかけになった作品だった。信さんによれば、三育の卒業式ではベートーベンの「月光」を最もうまい生徒がピアノで演奏したといい、マリヤも三育でピアノを習得し、戦後のパラオで教会音楽や、音楽教育を支えた。そんな話をすると、信さんがパラオからの留学生もいたと話してくれた。
「パラオの酋長の息子さん、サクマさんていました。彼ほどいろんな本を読む人はいなかったです。一級下でした。学生が作った二階建て寄宿舎は、サクマさんが歩くとゆったりゆったり、ドスンドスンとね、体格がよかった。文学の本を色々読んでいた」
思いがけないつながりに嬉しくなる。

やがて卒業を控えた年に、文部省の役人が学校にやってくる。セブンスデイという宗派は、再臨(サバティカル)信仰だ。世の終わりにみんなが集められて裁かれるという信仰で、熱心な信者は「天皇も裁かれる」と答えた。
「それでこの学校はだめだと。当時は不敬罪があった。私が最高学年のときつぶされたのね。最後の学生」
昭和20年、信さんは12月繰り上げ卒業となり、そのまま徴兵された。本来20歳からの徴兵が兵隊不足のために早められていた。世田谷の野砲第七部隊に配属され馬の係を任される。アメリカがトラックで大砲を運んでいたとき、日本は6頭の馬で引いていたのだ。当時の信さんには音楽家になる夢があった。しかし、東京大空襲がやってくる。世田谷も軍事施設を中心に大きな被害が出た。
「空襲でけがしたんです。この指を切ってしまって神経がないんです。触ってもわからない。それで音楽はやめにしたんです。一番悪いのは戦争ですね。そういう風に自分の意志でなく道を曲げられた人多いと思うんです。だからそういう人々の味方となって支えていきたい、そういう使命を持ったんです。」
1940年10月17日には青山学院で「皇紀二千六百年奉祝全国基督教信徒大会」が開かれ、五郎さんは「新しい天と新しい知の幻を仰がしめたもうてまことにありがたく感謝いたします。すべての教派、教会が全く一つになるという出来事を目前に仰がしめ給うてまことに感謝いたします」と祈りの言葉を述べた。実際には、日本基督教団としてキリスト教プロテスタントの諸宗派が一つにまとめられたことは、政府の宗教への統制を強めることに他ならなかった。やがて、教団に所属していたホーリネス系の牧師らが治安維持法で大勢逮捕された際も、教団側は「皇国民たるの自覚に立ち、臣道の実践を志すことを求めた」「御当局において処断してくださったことは、教団にとり幸い」と歓迎のコメントを出すなど、御用団体のような実態になってしまっていた。五郎のコメントがどの程度、本心からのものかは知る由もないが、大会において祈りの奉読を依頼された時点で、このようなコメントしか出せなかっただろうと思われる。
信さんが徴兵されたとき、父の五郎さんはインドネシアのセレベスに宗教指導のための牧師として教団から派遣されていた。
「南方の方はクリスチャンが多かったから、行ってくださいと言われたようです。日本人は神社、寺ばかりじゃないと(伝えるために)、牧師たちが派遣されていった。一生懸命楽しく伝道してたらしい。信者さんもふえて、何百人て人が来て心開いて。父から聞きました。若かっただろうし、希望に燃えてたんでしょうね」
愛香さんも「現地の人が反日にならないように、牧師を送って楽しくやらせたようです。兵隊じゃないのに少尉とか中尉とかいい身分をもらって優遇だったらしいです。怖い思いもせず」と父のセレベス時代を語った。大きな流れの中でみたら、それは日本の国策の中で行われた植民地の現地民懐柔の一形態だ。しかし、個人レベルで見るときそこには、若い牧師の情熱があり、現地の人々との温かい交流と信頼関係が生まれていたことが想像できる。それならよかったじゃないか、とも言えるし、いや、けしからんじゃないかとも言える。大事なのは両方の視点を失わないことのような気がする。
1941年に始まった日米開戦はキュックリヒと北米の福音教会との関係を悪化させ、連絡も資金も途絶えたという。牧師不在の中、キュックリヒは教会の仕事と子供たちの世話に明け暮れた。しかし、とうとう空襲によって焼け出され、ドイツ大使館の翻訳で糊口をしのぐことになる。やがて、枢軸同盟国の国民ということで滞在を許されていたドイツ人たちも河口湖の富士ビューホテルに強制的に移され、不便な暮らしが始まった。そんな中、日本語のできたキュックリヒは従業員とも親しくなり厨房仕事を手伝っていたという。藤崎家の愛香さんら幼い子供たちは母方の親戚のいる弘前へと疎開した。

終戦後、焼野原となった上野でキュックリヒが戦災孤児に出会い、孤児たちのための施設を作る決意をしたことは、第1回で触れた。向島教会に通っていた岡安寿々、正庫母子が加須にあった岡安ゴム工場の宿舎を用意したのだ。寿々さんたちは、地元民から反対の声があがっても熱心に説得を続け、理解を得たという。その後も寿々さんは主にお金のことや市や県とのやりとりなど対外的なことを担当し、キュックリヒは現場の教育に立った。同時に、必要があれば園の外へも出ていった。引揚者の生業とするための駅前マーケットの開設や、1947年のキャサリン台風での救援活動など、そのとき必要なことに積極的に取り組んでいった。
7歳だった愛香さんは加須の愛泉寮宿舎で育つ。食べ物もろくになく、アメリカの教会からのララ物資*1で山羊をもらったことを覚えている。キュックリヒは慣れない乳しぼりにも率先して取り組んだ。みなが貧しさにあえぐなか、働きたい母親たちが子供を預けるための保育所は求められていた。
「学校に通う孤児たちを送り出した後、100名くらいの青空保育でした。夕方お母さんたちが迎えにくるまで。それから学校から孤児たちが帰ってくるので風呂に入れたりご飯食べさせたり。本当に大変な毎日だったと聞いています。やがて青い目の混血児もどんどん入ってきました。日本人とアメリカの兵隊さんとの子でしょう。キュックリヒはいろんな伝手をたよって養子に出していました。エリザベスサンダースホームがよくとりあげられますが、こちらも沢山やっていましたよ」
エリザベスサンダースホームは1948年沢田美喜が大磯町に作った混血児のための乳児院だ。地元の小学校のPTAからホーム出身児童の入学への反対があったこともあり、53年には学齢に達した子たちが通えるように聖ステパノ学園も作られた。神奈川ではエリザベスサンダースホームが、埼玉では愛の泉がそれぞれ同じように混血児の養子縁組を実現させていた。
「アメリカやオーストラリアへね。横浜に送りに行ったり。籍もはっきりせず、ただ生まれたけれど、アメリカは子供が欲しいひと多いからよかったんじゃないですか?」
愛香さんは、アメリカに渡った「メアリちゃん」を後日キュックリヒと訪ねたという。
「ロシア人、中国人、日本人と預かっている大学の先生のおうちで、自分の部屋ももらってクローゼットがあって、メアリちゃんの服がだーっと入っているわけ。加須とずいぶん違う生活だなあと口あけてみていました」
ノンフィクション作家の石井光太は戦争孤児を調べる中で、中野の「愛児の家」の石綿さたよを取材しているが、ここで預かられた混血児も「メリー」と名付けられている。
パッと思い出せる外国人の名前がそれしかなかったのだ。
さたよはメリーちゃんをどう扱うかについて悩んだ。彼女は一目で外国人とわかるような顔立ちだった。成長するにつれ、周りからは「パンパンの捨て子」として激しい差別を受けて生きていかなくてはならなくなる。
(『浮浪児1945- 戦争が生んだ子供たち』)
日本にたくさんの「メリーちゃん」が生まれた時代、こうした混血児への差別については、私も神奈川の基地のそばで育った知人から聞いたことがある。知人といっても彼は私より30歳ほど上だ。1950年代から60年代にかけて少年だった人だが、「混血児は障がい者学級に入れられていた」というので驚いた覚えがある。もちろんひどい差別的対応だ。しかし、大磯でステパノ小学校を作らざるを得なかった背景に、大磯小学校PTAから、混血児が「我子が机を並べて学ぶのはいやだ」という主張があったことを考えると、当時の感覚としては健常者の子供たちと混血児を分けるという発想は、残酷だがありふれたことだったのかもしれない。
沢田は53年から数回ブラジルへ視察へ行くと、土地を買って農業移民として行先のない子たちを送る決意をして2回10名を送っている。この時代は、引揚者として着の身着のまま日本に帰り、苦労を重ねていた人々が、よりよい暮らしを求めて南米への戦後移民となり、再び日本を出ていった時代でもある。結果的に、入植先でも日系移民たちとの関係がうまくいかず、入植は途切れてしまったというが(上田誠二『「混血児」の戦後史』)、それほどまでに、彼らを海外で暮らさせてあげたいという思い、裏返せば日本で生きていくのは不可能である、という思いを抱いていたということに、当時の社会の差別意識の強さについて考えさせられる。
愛泉寮からアメリカに渡った混血児の中には、厚木のキャンプに兵役で滞在し、30年後に愛泉園を再訪した者もいた。昭和24年にアメリカに渡ったトミーは実母に会いたいという願いを抱いて、相談に来たのだった。職員たちは富山にいたトミーの母親を探し当て、二人の再会を実現させたという。
混血児のいた時代から現在まで続く「愛の泉」も、時代のニーズと共に機能を拡張してきた。愛香さんは30代から乳児院に入り指導員として園長だったキュックリヒと共に関わるようになった。
「ここもだんだん母子家庭や、虐待児がでてきました。喜怒哀楽が少ないんですよね。うれしいとか怒るとかっていうのが抑えられちゃう、どうしても。ここも職員は8時間しか働けないから、夜勤をいれながら。その中でどうやって一人のお母さんになるか。大人の顔色をのぞくような子供にはしたくないですからね。大事なのは職員が楽しく働いてくれること。子供に優しくできるから、そしたら子供もおおらかになる」
シンプルだが、職場の雰囲気というのは介護や福祉の現場でとても大切なことだと思う。やまゆり園での大量殺人を引き起こした植松という青年が、最初は真面目に職務をこなし、担当する障害者のことも「かわいい」と感じていた、というニュース記事は、驚きをもって読んだが、記事は職場関係者への取材をし、現場の雰囲気に植松が悪い意味で染まっていっただろう可能性を伝えていた。保育や介護というのは、生半可な知識や気持ちだけでは続けられないものだと思う。そこで働く者が苦労しつつも、生き生きと楽しく働けているのか、という点は決して見逃されてはならないだろう。

キュックリヒは78歳で永眠したが、74歳の宣教50周年には記念の贈り物は何がいいか尋ねられ、「子供たちお年寄りみんなが休めるベンチと藤棚がほしい。他には何もいりません」と答えた。キュックリヒがイメージした通り、「愛泉園」園内で様々な人が憩う場になっているという(『G.E.キュックリッヒの生涯』)。彼女のイメージのすべてが未来につながっていたのだ、と思う。周りの他者を思う気持ちの先に未来が生まれ、現在の愛泉園がある。
繰り返しになるが、鐘紡の社史には鐘紡の社史には、キュックリッヒの貢献はおろか、バーンファインドと工場長の藤らが協力して鐘紡敷地内での建設に漕ぎ着けた鐘ヶ淵向島教会のことは全く出てこない。しかし、資本主義的企業経営のためにと、鐘紡経営陣が積極的に取り入れたキリスト教は、思いがけない形で女工たちへの宣教、女工たちの子供の保育という場を生み出し、兵庫工場に後れを取っていた東京本店の福利厚生の充実を実現させていった。また向島教会には、岡安母子が熱心に通い、キュックリヒと固く結ばれた信頼関係が、戦後の戦災孤児の保護、養育という形で、場所を埼玉の加須に移して発展し、社会福祉法人「愛の泉」として健在である。
キュックリヒは72歳のとき地元への貢献者として認められ、加須市名誉市民となっているが、向島においての痕跡はほとんど残っておらず、事実も十分に知られていない。そんな中、今一度、墨田において鐘紡と結びついて興ったキリスト教的福祉の展開と、そこから戦後の加須の地にキュックリッヒが根付かせた「愛の泉」への流れを追ってみたかった。
バーンファインドは「Wayside Sowing」(路傍に種をまく)という自伝を1914年に著したが、キュックリッヒもまた種をまく人であり、ドイツ、アメリカ、向島、加須と移動しながら信仰を持ち続けた人生はそれ自体、種を運ぶひとひらの綿毛のようでもある。彼女の信仰の花はかつて向島に咲き、いまなお加須の地で花開いているのだと思う。

*1 LARA(ララ)(アジア救済連盟)によって供与された食料や衣類などの物資
協力:すみだ郷土文化資料館
NPO法人トッピングイーストが企画・運営した、音楽とアートのフェスティバル『隅田川怒涛』のいちプログラムとして、寺尾紗穂、青葉市子、小林エリカによる女工の物語を題材にした映像作品「女の子たち 紡ぐと織る」を制作しました。
レポートと合わせてぜひご覧ください。